 
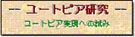


|
 ユートピア概論 ユートピアとは トーマス・モアのユートピア ユートピア実現事業 ユートピア実現の試み事例 1.ピューリタンの民主主義社会 2.クエーカーたちの理想都市 3.シェーカーズ教徒村 4.イエズス会のミッション 5.ユートピア社会主義者の夢 6.オーウェンの協同組合 7.フリエの生産・消費協同社会 8.ロシアの農民ユートピア国 9.トルストイの「イワン王国」 10.ガンジーの「インド独立国家」 11.武者小路実篤の「新しき村」 12.毛沢東の「人民公社」 13.伊藤勇雄の人類文化学園 14.農大生たちの「杉野農場」 15.ブラジルの弓場農場 16.シュタイナー「ひびきの村」 17.ヤマギシ会「ヤマギシの村」 18.脱日本運動の「ノアの方舟」 19.パラグアイのメノニータ社会 20.モルモンの理想郷ユタ 21.アドベンチストの学園村 22.イスラエルのキブツ 23.エホバの証人の地上天国 24.デンマークの共同体 25.ヒッピーの生活共同体 26.マレーシアのイスラム村 27.ドイツの学生生活共同体 28.宮沢賢治のイーハトーブ 29.宮崎駿のユートピア文学 30.南米の理想郷「インカ都市」 31.国宝美術作品の理想郷図 32.未来都市ブラジリア 33.都市工学のユートピア「海市」 34.宇宙空間のユートピア計画 35.ユートピア的企業例:トヨタ 36.ユートピア社会造り企業:松下 37.ユートピアを模索する産業 38.ユートピア商売のリゾート産業 39.フィンドホーン共同体 40.生産勤労共同体「共働学舎」 41.共生共存企業「わっぱの会」 42.無所有奉仕共同体「一燈園」 43.小さな共同社会「癒しの郷」 44.宗教的社会福祉企業の大倭教 45.理想的社会造りのNPO ユートピアの条件:自給自足 1.自給自足の生活と概念 2.自然農法、有機、無農薬他 3.自給自足を目指した試み 4.本サイトの結論
ラテンアメリカはいかがですか ブラジル パナマ 国際サバイバル道場   
2.「コルホーズ」 学研学習事典データベース より 3.自分の足で立つ 4.ロシアの夢 |
 1917年の革命で権力の座についた共産党は、社会主義の理念にもとづいてまずロシア国内の工業の国有化を実現させた。ついで1920年代の末から30年代の初めにかけて断行したのが農村における集団化である。それまでの農業は地主や小作人による個人経営の形で行なわれてきたが、ソビエト政権は伝統的な村を基盤にコルホーズと呼ばれる集団農場を組織し、耕地や家畜や農業機械などをその共同所有としたのである。コルホーズの結成にさいしては貧しい農民が利用され、勤勉な篤農家は富農として排除されることが多かった。富農のレッテルをはられた農民は家族をあげて僻地へ追放された。1930年代以後ソビエトでは、コルホーズがソフホーズ(国営農場)と並んで農業の経営主体をなすことになった。もっとも農民は世帯ごとに自宅のまわりに一定の広さの野菜畑を保有すること、乳牛やにわとりなど若干の家畜を飼うことなどは許されていた。 【農業集団化】  1923年,レーニンは「協同組合について」のなかで,すでに農業の社会主義的集団化の必要を説いたが,本格的な農業集団化が始まったのは第一次産業5カ年計画初期で,その基本的完了は第二次5カ年計画の終期である。すなわち,1927年12月第18回党大会で農業の集団化が決定され,1928年6月コルホーズ代表者大会を開催,10月第一次5カ年計画が実施に移されて,社会主義工業化政策が推進されるとともに,ネップ期に成長した富農(クラーク)を絶滅し,農業の社会主義化を遂行するためにその集団化政策が推し進められた。1928年11月,農作業の機械化を促進するための機械トラクター=ステーションの設立,1930年1月5日の「集団化の速度と集団農場建設に対する国家の補助について」の布告とともに,農業集団化は具体化され,コルホーズに対して5億ルーブルの融資がなされて国家の負担による耕地整理の実行が保障された。こうして,1932年には農民経営の61.5%がコルホーズ化され,約1,500万戸の農家が総播種面積の75.5%を含む21万1,000のコルホーズに結合された。その生産高も1928年の総農業生産高の3.3%から,76.1%へ上昇した。
1923年,レーニンは「協同組合について」のなかで,すでに農業の社会主義的集団化の必要を説いたが,本格的な農業集団化が始まったのは第一次産業5カ年計画初期で,その基本的完了は第二次5カ年計画の終期である。すなわち,1927年12月第18回党大会で農業の集団化が決定され,1928年6月コルホーズ代表者大会を開催,10月第一次5カ年計画が実施に移されて,社会主義工業化政策が推進されるとともに,ネップ期に成長した富農(クラーク)を絶滅し,農業の社会主義化を遂行するためにその集団化政策が推し進められた。1928年11月,農作業の機械化を促進するための機械トラクター=ステーションの設立,1930年1月5日の「集団化の速度と集団農場建設に対する国家の補助について」の布告とともに,農業集団化は具体化され,コルホーズに対して5億ルーブルの融資がなされて国家の負担による耕地整理の実行が保障された。こうして,1932年には農民経営の61.5%がコルホーズ化され,約1,500万戸の農家が総播種面積の75.5%を含む21万1,000のコルホーズに結合された。その生産高も1928年の総農業生産高の3.3%から,76.1%へ上昇した。【農業集団化の障害とその後の変化】 農業集団化は従前の農業機構をまったく破壊しようとしたもので,社会の質的変革でもあったから,一方では社会的混乱を引きおこした。極貧農を除くすべての農民は高税に悩まされ,富農とみなされたものは,財産・土地を没収され強制労働所に送られた。多くの農民が逃亡し,また反抗した。したがって農業生産は低下し,1930年〜1931年には飢饉がおこった。しかし,集団化は強権をもって進められ,1937年4月までに全農家の93%,2,500万戸の農家が集団化され,その播種面積は全播種面積の99%,1億1,700万ヘクタール,その生産高も全農業生産高の90%に近づいた。1949年からコルホーズの統合が行われ,その数は1937年24万9,000,1940年23万6,900,1954年9万,1968年3万6,000,1981年1万6,000と変化した。個々のコルホーズは大型化し,その構成農家戸数・農地面積は増大している。1940年1コルホーズあたり農家戸数81,農地面積490ヘクタールであったのが,1968年には,農家戸数420,農地面積6,100ヘクタール(播種面積は3,000ヘクタール)となった。コルホーズが技術的経験と経営技術を身につけ一本立ちできるようになると,1958年MTSは廃止され,その農業機械はコルホーズに売却されて,修理技術ステーションに改組され,1961年設立のサユーズ=セリホズ=チエフニカ(技術公団)の一部局となった。
山村理人、「チェコ、スロバキアの事例を中心とした分析」より
10月革命によって成立したソヴェト体制の下で,ロシア思想史は表面的には,完全に断絶したかに見える。しかし少なくともスターリン体制確立前の1920年代,いわゆるネップの時期には,革命前に形成された諸思想が,一定の,しかも強い政治的な枠をはめられながらも,ロシア国内で維持され,形を変えながら再出する局面があった。革命前にロシア・マルクス主義と対抗しつつ大きな力をもった,ナロードニキ主義やロシア自由主義の思想的潮流(その主流は国外追放,亡命を余儀なくされた)が、いわゆる「党=国家体制」の鉄枠の内部に,細々とした形ではあれ,流れ続けていた。 ネップ期に、ソヴェトロシアの国家農業機関に積極的に参画し,ロシア農村の「協同組合的集団化」の構想を提起した農学者,A・V・チャヤーノフの思想は興味深い。 今、欧州の旧社会主義諸国の農村では、歴史上かつてないユニークな「実験」が行われつつある。旧体制が崩壊してから、これらの国では社会主義の「負の遺産」を清算すべく農業構造改革が始められ、10年が経過した。そして、現在、われわれが目にするものは、改革が始まった当時は誰もが想像も出来なかったような他に類を見ない農業の形態・構造(生産組織の構造や土地関係など)であった。特に、我々にとって興味深いのは、これらの国々で活動する多様な農業生産組織の存在である。すなわち、伝統的なコルホーズ型集団農場の組織再編によって生まれた新しいタイプの農業生産協同組合や大規模会社農場(株式会社、有限会社)、国営農場が分割・私有化される中で現れた私営農場、小人数によるパートナーシップ経営、多数の雇用労働を用いた「資本家的」個人農場、市場指向型のフルタイム家族農場、自給的零細生産者など、多様な生産組織が併存し競争するという極めてユニークな状況が生まれている。こうした状況は、さながら「生産組織の研究のための一種の実験場」のようなもので、これらの国を訪れれば、通常の資本主義諸国では殆どみることの出来ないような様々な農業生産組織を観察し、その組織の特性や効率性を調べ、相互に比較することができる。 本稿は、ポスト社会主義の農業生産組織の問題について論考することを目的とするが、上に述べた多様な形態の中で特に社会主義時代の集団農場、国営農場の資産を継承して生まれた様々な大規模農業生産組織(農業企業)を中心的な分析対象としてとりあげる。 体制転換後に東欧諸国や旧ソ連の農村で行われた改革は、農地や農場資産を集団化前の旧所有権者に再配分すること、あるいは国有資産を新たな所有者に売却・移転することを中心的な内容としたものであった。当初、こうした改革により社会主義時代の巨大農場は解体されて西側の国々で通常見られるような農業構造(すなわち家族農場中心の構造)に移行していくと考える者も多かった。確かに、バルト海諸国、コーカサス、東欧ではバルカン地域で、旧体制崩壊後、「非集団化」のプロセスが急速に進んだ。しかし、その一方で、一連の国々では、社会主義時代の農場を継承する大規模生産組織が様々な変化を受けながら生き残り、農村における中心的な存在として活動し続けている。 本稿では、このような国々の中で、主としてチェコ共和国とスロバキアの事例をとりあげながら1、社会主義時代の農場を継承した大規模農業生産組織が移行経済の条件下で、経営体としてどのような組織の変化をとげているのかを検討する。そして、ポスト社会主義農業企業がどの程度の「生存能力」や経営としての安定性を持つのかという点を考察し、将来における農業構造の変化の方向についての展望を与える。 1. 移行経済諸国における農業生産組織の多様性 最初に述べたように、社会主義時代に全面的な農業集団化を行なった欧州の旧社会主義諸国では、体制転換後、多様な農業生産組織が現われ併存した状態となっているが、これらをどのような概念と用語で表現するのかが問題になる。移行経済諸国における農業構造をとりあげた議論の中では、しばしば概念や用語の混乱が見られ、これが正しい理解を妨げている場合がある。そこで、論を進める前に、最初に、生産組織に関する概念の整理と用語確認を行なっておく必要があるだろう。 (1) 農業企業と農業生産法人 移行経済諸国では、農業生産法人には、様々なタイプがあり、個人農場や家族農場で法人形態をとるものもある。しかし、それらの多くは、普通の家族農場の組織と比べると、はるかに大きな人員(数十人〜数百人)と組織構造を持った農業経営であり、普通は、生産協同組合、株式会社、有限会社のような法人形態をとっている。本稿では、これらの農業生産組織の総称として「農業企業」(agricultural firms)という言葉を使用することにする。この場合、企業というのは法律的概念ではなく、経済的概念(かつてロナルド・コースが「企業の本質」を論じた時に使ったような意味での)として使われていることに注意されたい。 「農業企業」とは、農業生産法人と同義の言葉ではなく、前者が大規模組織による農業経営全般を表現する経済的概念であるのに対し、後者は経済的には全く異質のものを混在させる法律的概念である。移行経済諸国における大規模組織の農業経営に対して農業生産法人という言葉を使わないのは、それが法律的概念であるために現実の経済現象を説明する際にしばしば混乱をもたらすからである。たとえば、大規模組織(企業)ではなく実質的には家族経営であっても、法人形態をとる場合(家族法人)がしばしば見られる一方、実態的には企業であっても法律的には自然人であるような個人所有の農場も存在する。 農業企業には、生産協同組合、株式会社、有限会社、パートナーシップ、非法人の個人経営など様々な法律的形態が含まれる。この概念は、体制転換の後も農業の全面的な「非集団化」が起きなかった一連のポスト社会主義国での農業構造の1つの特徴を表すキーワードである。 (2)「大規模農場」という概念について 「大規模農場」(large-scale farms)という言葉は非常に頻繁に使われるものだが、農業企業と同じものを表現しているケースが多い。ただし、大規模農場の「規模」とは、土地面積や家畜頭数といった物的指標と直接結びつくような印象を与えるが、農業企業における規模概念は物的指標の大きさではなく経営組織の規模について考えている。 組織の規模と土地面積や家畜頭数などの「物理的規模」とは相互に規定しあい結びついているが故に2つの概念はしばしば明確に区別されずに融合した形で使われており、「大規模農場」という用語が使われている場合、こうした曖昧性が残ってしまうという問題がある。しかし、物理的規模は相対的に大きくても小さな組織(家族や小人数のパートナーシップなど)で行われている農業経営体もありうることからわかるように、経済的分析を行なう場合は、両者をちゃんと区別して考えなければならない。この意味で、本論では、誤解を与えやすい大規模農場という用語を避けているのである。 数年前に出たOECDによる移行経済諸国の農業に関する報告書の中に、農場構造を扱った部分がある。そこでは、東欧諸国の農場を面積に応じて「小規模農場」、「中規模農場」、「大規模農場」に区分し、東欧諸国では体制転換後の農場私有化、多数の私的土地所有者の誕生にも関わらず、「大規模農場」がなくならずに存続しているということが指摘されている(OECD 1996, pp.145-148)。これも、物的規模指標でみた小規模農場と大規模農場の効率性やviability を比較しようとする伝統的発想にそったものである。本論では、こうしたアプローチはとらない。 なお、この問題は、いわゆる「規模の経済」(scale economies)を論じる時に重要な意味を持つ。それは、通常、物的な生産規模による規模の経済のことなのであるが、一方、組織の規模の方は、それとは別の次元の問題である取引コスト(transaction cost)の問題に関わるものである。大規模組織の効率性はこの両者の問題がからみあったものとして考察されねばならない。 (3) 会社農場 東欧各国の統計や農業をあつかった論文等には、しばしば、「会社農場」(company farms) という概念が現れる。これは、株式会社や有限会社といった会社法人組織をとる農場の総称で、同じく法人である農業生産協同組合と対比する意味で使われることが多い。既に述べたように、農業企業という用語の方は、多数の従業員を抱えた大規模な組織による農業経営の総称を指しており、その中には会社農場もあれば農業生産協同組合も含まれる。しかし、会社農場や農業生産協同組合が農業企業であるとは必ずしも言えない。 注意しなければならないのは、株式会社や有限会社というのは経営の法的形態のことであって、農業生産組織の現実の組織としての特徴(労働組織、意思決定構造、所有構造など)そのものを示しているわけではないということである。経営体がその組織を実質的に殆ど変更することなく法的形態だけを変更することも可能である。 特にこれに関連して指摘しておく必要があるのは、生産協同組合と会社農場の区別の問題である。この区別が移行経済諸国ではミスリーディングな場合がある。形の上では「株式会社」や「有限会社」として登録されていても、現実の組織は生産協同組合にほぼ等しいような農場もしばしば見られる。農場従業員がそのまま株主や有限責任社員となっていて、しかも株主総会や社員総会での意思決定が古典的な協同組合原理である1人1票に結果的になってしまっている(所有シェアが均等に分散していれば結果的にそうなる)場合は依然として会社農場は生産協同組合と殆ど同じものであると考えねばならない。 たとえば、後に見るように、チェコやスロバキアでは、協同組合農場の株式会社への転換が、しばしば、資産保全のための一種のトリックとして行われており、その場合、株式会社といっても旧組合員の間に所有が分散化し、実際には所有構造の上でも意思決定構造の上でも生産協同組合の場合と殆ど大差がない場合がかなり見られる。もちろん、法人形態を変えたために将来、組織の性格が変わっていく潜在的可能性が与えられたとみることは可能であるが、いずれにせよ、法的形態と現実の組織のあり方の間にはしばしばズレがあるということに注意すべきなのである。 (4) 集団農場と農業生産協同組合 旧ソ連のコルホーズに代表されるタイプの農場は、形式上は生産協同組合の一種と位置づけられているが、実質的には協同組合とは性格がかなり異なるものであり、本稿では「集団農場」(collective farms)と呼ぶことにする。東欧諸国で社会主義時代に「農業生産協同組合」と呼ばれていた農場の多くはコルホーズ・タイプのものであり、「集団農場」の範疇に入れられる。 集団農場は、形の上では確かに協同組合のようであるが、構成員が土地や資産の提供者であるという側面が非常に弱く(法的にも、意識の上でも)、彼らはもっぱら労働の提供者である。生産協同組合は、経済理論家たちによって、「労働者管理企業」(labor-managed firms、労働者1人当たりの付加価値最大化を目標とする企業)の枠組みで分析されることが多いが、集団農場にはこれは殆どあてはまらない。なぜならば、経営の最終成果(利潤や付加価値)と個々の構成員の関心が殆ど結びついていないからである。集団農場の構成員の主要な関心は賃金と雇用である。コルホーズ的集団農場では、管理統御形態は位階的であり、経営者の権力は生産協同組合に比べずっと強く、むしろこの点で資本主義的な企業経営に近い特徴を備えている。ただし、従業員は農場構成員の総会を通じて経営の意思決定に関与する潜在的可能性があり、資本主義的企業における単なる雇用労働者とは異なる。しかも、社会主義末期には、多くの国で協同組合における「労働者自主管理」的要素が強まり、経営者の人事に農場員が影響をより強く持つようになっていた。 体制転換後、多くの国では、集団農場の新しい協同組合組織への転換がなされ、構成員が土地や資産の提供者であるという側面が大幅に強められた。東欧諸国の「転換」された協同組合農場では、利潤がある場合、構成員には出資額に応じた配当が支払われるようにもなった。一方、ロシアなどの旧ソ連諸国では、この「転換」が徹底したものではなく、多くの農場は依然として「集団農場」としての性格を濃厚に残している。東欧諸国の新協同組合農場の場合も、組織転換によって完全に集団農場時代の性格が払拭されたとは言い難い。集団農場と生産協同組合の区別は理念的・モデル的なものであり、実際の農場組織をこれによって厳密に分類することは難しい。移行経済諸国では、両方の性格を持っているような中間的タイプが多く見られる。 (5) 「個人農業経営」と家族農場 移行経済諸国の農業統計では、しばしば「個人農業経営」(individual private farms)というカテゴリーが使われる。「個人農業経営」というと、家族農場(ファミリー・ファーム)を指すものと単純に考えがちであるが、この言葉はミスリーディングなものである。というのも、ヨーロッパの移行経済諸国では、主として家族労働に依拠して営まれる家族農場とは全く異なる「個人農業経営」が重要な意味を持っているからである。 ロシアや東欧諸国では、土地面積でいうと数百ヘクタールから数千ヘクタールにも達する規模をもち、多くの雇用労働者を利用するような個人所有の農場が存在する。そして、しばしば、それらは如何なる法人形態もとらず自然人として登録されているので、統計では通常の家族農場と同じカテゴリーに入れられている。たとえばチェコの例をあげると、「個人農業経営」(自然人)として登録されている農業者は1998年末の数値で合計2万3千あったが、そのうち、500へクタール以上の面積を経営するものが252農場、「個人農業経営」の総農地面積の33%を占めていた。これらの農場で従事する労働者の数は合計4576人であり、1農場当たり平均18人ということになる(MACR 1999, p.76)。これらの中には、国有農場資産の私有化の過程で生まれた「個人農業経営」、協同組合農場の幹部がその資産を移転してつくった「個人農業経営」、返還資産を出発点とし多額の補助を受け急速に資本蓄積した「個人農業経営」などが含まれると考えれる。 こうした「個人農業経営」における作業は、技術的には会社農場や生産協同組合等の法人農業企業と大差がないものであり、両者の区別は法的地位の違いに基づくものに過ぎない。もし、これらが税制上の理由等により法人組織に変わったら、統計上は「会社農場」というカテゴリーに分類されることになる。したがって、統計の中の「会社農場」の中にも、「大規模個人農場」というべきものがかなり含まれているだろうことが推測されるわけである。 これに対し、本稿で家族農場(ファミリー・ファーム)と呼ぶものは、法律的概念でもなく、統計的カテゴリーでもない。それは、単に家族が所有経営している農場という意味ではなく、主として家族労働に依拠して営まれる経営であるという意味を含んだものである。従って大量の雇用労働力を用いた個人所有あるいは家族所有の農業経営は、家族農場ではない。それらは、本稿の用語法では、農業企業の1形態である。 チェコの農業経済学者トマシュ・ドーハは、チェコにおける「個人農場」というカテゴリーの中には、次の4つの異なる種類のものが含まれていると述べている(Doucha 2000, p.34)。 1)自給的経営 2)所得指向型個人経営 3)利潤追求型個人経営 4)estate farms(雇用労働のみに依拠する大規模個人経営) このうち、2)と3)の違いは、前者が雇用労働力も使うが、主要な労働力は家族員による経営であり、後者は家族労働も使うが、主要な労働力は雇用による経営という点である。理論的には、農業企業と対比して考察されるべきものは、家族農場であって、上のように雑多な種類の組織を含む「個人農業経営」一般ではない。 (6) 「資本家的」農業経営 企業的農業生産組織の中の1つのサブ・カテゴリーとして、多数の雇用労働者を用いて営む農業経営体のことを「資本家的農業経営」(capitalist farms)と呼ぶことがある。これは、もともとは、ロシアの農業経済学者アレクサンドル・チャヤーノフが「勤労農民経営」(これは本稿で家族農場と呼んでいるものとほぼ同じものを指す概念である)と対比させる目的で好んで用いた概念であり、筆者もロシア農業を論じた著作(山村1997)の中で一部、この概念を利用している。「資本家的」という言葉は、ここではミクロの経営組織上の特徴を示すもとのとして使われている。すなわち、経営組織の観点からもっぱら雇用労働に基礎を置く企業経営を家族労働を中心とする家族経営と区別して「資本家的」と呼んでいるのである3。なお、ドイツの農業経済学者、ギュンター・シュミットが、"Large hired-labor farms" あるいは、"Large capitalist farms"という言葉を使ってこの種の農業経営を表現しているが(Schmitt 1993)、これもチャヤーノフ的な概念を意識したものであろう4。 資本家的経営は必ずしも株式会社や有限会社のような会社農場の形をとらない。雇用労働のみに依拠する大規模「個人農業経営」も資本家的経営の一種であることはその定義からも明らかである。逆に会社組織をとっていても、その実態が家族労働中心の経営であるならば、それは資本家経営の範疇には入らないだろう。また、生産協同組合は資本家的経営の中には入らないが、東欧の協同組合農場の一部には、所有構造や意思決定構造が変質して有限会社に近いようなものになっている場合がある。その場合、「生産協同組合は資本家的農業経営に変質しつつある」といった表現が可能になるであろう。 2. 農業企業(旧社会主義農場)の存続を規定する諸要因 社会主義時代に農業集団化を達成した国々では、いずれも国有農場や協同組合農場などの農業企業が大半の農地を利用していたわけだが、現在では、農業企業の占める比率は国によって大きく異なっている。バルカン地域のアルバニア、ルーマニア、旧ソ連のコーカサス諸国やバルト海諸国のように個人経営(この意味については前節を参照)のシェアが非常に高くなった国がある一方で、中欧のチェコ、スロバキア、ハンガリー、旧東ドイツ、旧ソ連のロシア、ウクライナなどでは、農業企業の比重が以前として大きい。本節では、同じように農業集団化を経験した国々でありながら、どうしてこのような農業構造の違いが生まれてきたのか、その要因について考察する。 (1) 旧所有権の返還・回復(restitution) 政策の影響 Swinnen とMathijs は、個人経営の土地面積比率が大きくなっている国は、(1)集団農場労働者への土地配分比率が大きい、(2)農業人口の比重が大きい、(3)既存農場からの退出コストが相対的に小さい、という特徴を持つことを指摘している(Swinnen and Mathijs 1997)。 これに関連して特に注目されるのは、集団化された農地の旧所有者への返還・権利回復(restitution)を実施した国々で、農業企業の比重が大きくなっているという点である。旧所有者への返還・権利回復は当初、集団農場の崩壊を促進する政策であると見るむきが強かったが、実際には、それは逆に集団農場およびその継承法人の存続・延命を助ける作用があったと見るべきである。本論文集の中の別稿でも論じているように、旧所有者への農地の返還・権利回復は、土地利用から分離した零細で分散的な土地所有を大量に作り出し、これは集団農場およびその継承法人の土地利用を継続させる上でむしろ好都合なものとなった。 土地やその他の資産が集団農場の労働者に配分される場合には、個人経営の創出コストは相対的に低く抑えられるので、個人経営の比重が大きくなる。アルバニアのケースはいうまでもないが、ラトビアのように、旧所有者への土地返還という方式が採用された国でも、結果として農村の労働者へ土地が多く配分されたケースでは、個人経営の比率が高くなっている。 逆に、スロバキアのように、集団化前の農村において土地無し農業労働者の比重が高かった国では、土地所有権の返還によっても農場労働者には土地が殆ど分配されず、そのことで、個人農化がむしろさまたげられることになった。スロバキアでは、農地利用に占める協同組合農場の比率が他に比べ著しく大きく、個人経営の占める比率は数%に過ぎないが、これはチェコとの分離後のメチアル政権時代における「協同組合重視の政策」のせいというよりも、むしろ、チェコスロバキア時代に決められた旧所有者重視の政策のおかげといった方がよい。 (2) 集団経営のリスクシェアリング機能 農業企業の生き残りを説明するもう一つ重要なファクターは、集団経営の持っている「リスク・シェアリング」機能と農業労働者の危険回避指向があげられる。Michael Carter は、中南米の経験に基づき、集団経営はリスク・シェアリングのメリットがあり、非集団化に伴い労働インセンティブや生産性は増大してもリスクや不安定性の増大という問題が起き、両者の間にはトレード・オフ関係があるという議論を展開した。彼によると、特に伝統的な小農経済ではなく、購入投入財に強く依存する近代化された農業ではこのリスクの問題が非常に重要となる(Carter 1987)。 筆者のみるところ、ロシア、ウクライナなどの旧ソ連諸国で集団経営の比重が依然として高いのは、このファクターが決定的な役割を果たしていると考えられる。これらの国では、市場経済を支える法律や制度が未発達で、所有権も不明確なため、個人経営を行なうためのリスクが非常に大きくなっている。しかも、体制転換後の農産物需要の減少と輸入農産物の圧力により、個人経営のリスクをおかすには農業をとりまく経済的条件があまりにも悪くなりすぎた。これがロシアなどで、商業的個人経営が発展しなかった主要な原因である。 旧ソ連諸国ほどではないが、東欧でも、個人経営をやるためのコストとリスクは非常に大きくなっている。このコストとリスクを大きくしている1つの大きな要因は、個人経営をサポートするシステムの欠如である。特に、重要なのは、集団化によって農業協同組合(生産協同組合ではなく個人経営にサービスを提供する協同組合)の伝統が失われ、体制転換後の現在も、個人経営のための協同組合組織が欠如している点である。農業企業で働く多くの農業労働者は、専門的技能という点では優秀の者も多いが、経営者としての資質に欠けている場合が多い。それをカバーする機能を持つのが協同組合組織だが、それが存在しない東欧諸国の現状では、一般農業労働者が個人経営をやるのは、非常にリスキーなものとなっている。こうした状況の中で個人経営をやる能力とリスクを負う勇気を持つ者は、一般農業労働者ではなく、むしろ集団農場や国有農場の指導者・幹部だった者たちの中に見出すことが出来る。実際、ロシアや東欧諸国では、規模の相対的に大きい有力な個人農場が、しばしば元指導者、幹部によって経営されている例が多く見られる。社会主義時代の農場指導者が個人経営をやる場合に持つ優位点は、単なる農業技術的な専門知識以外のところにある。それは旧体制のもとでの様々な取引、交渉をやってきた経験やその中で培ってきた人脈(これは資本や市場へのアクセスを容易にする)であり、また多額の資金を取り扱う経験・感覚である。 欧州の移行経済諸国の個人農業経営の現状を見ると、少数の大規模経営(雇用を多数用いる資本家的経営)と多数の自給的零細経営の両極端に別れ、中間層(本来の商業的家族農場の層)が非常に薄くなっている。これは、上に述べたことによって説明されると思われる。 (3) 規模の経済との関連 「規模の経済」のファクターについても触れる必要があるだろう。移行経済諸国における農業企業の存続は、しばしば、規模の経済の問題として論じられるからである。しかし、農業生産については、家族農場で可能な範囲を超えた規模では、規模に関して収穫逓増の法則は明瞭には働かないということを示した多くの研究がある6。したがって、農業企業の存続を農業生産における規模の経済の要因と結びつける根拠は乏しい。1991 を見よ)。それによると、米国の畑作農場の場合、面積規模が拡大すると生産費用は最初は低下していくが、すぐに費用曲線は水平(規模に関してコスト不変)の領域にはいる(L字型費用曲線)。しかも、この水平領域が始まるのは規模が比較的小さいところ(つまりファミリー・ファームで経営可能な領域)からである。しかし、農業における規模経済を考える場合、生産面だけでなく、投入財の購入や生産物の販売、金融(資金の調達)といった側面を考慮する必要がある。実際、農業生産よりも、むしろ、マーケッティング、投入財の購入、信用や情報提供、リスク・マネージメントについて規模の経済が存在する(Deininger 1995)。たとえ生産面で顕著な規模経済が見られなくとも、上にあげたような活動や機能において農場規模が大きいほど有利であるということになれば、「規模の経済」が農業企業を存続させる大きな要因であると評価することが可能である。 西側の多くの国では、農業生産は家族農場で行いながら、上にあげたような分野については協同組合がカバーするという補完関係が見られる。しかし、こうした分野での協同組合が欠如している移行経済諸国では、規模の経済が全体として強く働く可能性があると言えよう。実際、規模の小さい農業生産者は、移行経済諸国において、この面でより不利な状態に置かれている。 (4) 既存システムの「自己拘束」性 最後に考慮しなければならないのは、いわゆる「経路依存性」(path-dependency) の問題とである。社会主義時代に集団化を達成し、長期にわたって大規模組織のもとで農業を行ってきた国々では、農業技術、サポートシステム、関連するインフラや産業部門、農業に従事する専門家などの人的資源といった様々な要素が大規模生産組織を中心としたシステムを前提として発展してきた。こうした条件のもとで、「非集団化」を一挙に進めようとすれば、社会主義時代に大規模組織のもとで蓄積された技術や知識、スキルといった要素が失われることを意味し、制度転換のコストは非常に大きくなる。 ゼロから新しい制度をつくりあげるのは多大なセットアップ費用がかかるのであり、その意味で既存の経営制度を維持しようとする「自己拘束」(self-enforcing)的な力が働かざるを得ない。特に、社会主義時代に集団経営が一定の高い生産力水準に到達し、かなり成功したと考えられてきたチェコスロバキア、ハンガリー、東ドイツといった中欧諸国では、こうした側面を無視することは出来ない。これらの国の成功した集団農場の指導者・幹部たちは、社会主義時代に蓄積されたもの、達成されたものに対して誇りを持ち、改革によってそれらの達成物が失われることをナンセンスであると強く感じている。彼らの多くは、大規模農場の方が家族農場よりも優れていると信じている。彼らの多くは、自分たちの歩んできた人生や経験・知識の蓄積を農業企業の経営と結び付けており、どのような形であれ農業企業の存続を強く望んでいる。中には、集団農場を一種の大家族のように見なして、従業員の雇用を守ることを自分の義務と真面目に考える「父親的」な農場長も見られる。こうした農場指導者たちは、西側的な家族農場創設を目指した農業改革に反発し、伝統的農業企業を守るためのロビー活動を行なってきた。彼らの代表が、政府の要職について農業政策に強い影響を与える場合もしばしば見られる。 これに対し、西側指向の改革を進めようとするのは、農村に殆ど基盤を持たない大都市の知識人・専門家、一部の官僚である。また、現在では農業に生活基盤を持たなくなった旧土地所有者やその子孫たちも、「非集団化」政策を支持する層となり得る。たとえば、体制転換後のチェコスロバキアで、協同組合農場の存続を脅かすような資産再配分政策が実行されたのは、農村住民の支持があったからでなく、むしろ、旧所有者の子孫を多く含むプラハなど都市住民の支持があったからである。 3. 「転換」された農業生産協同組合 体制転換後も社会主義農場の継承法人が生き残った国々では、継承法人の多くは農業生産協同組合の形をとった。たとえば、チェコ、スロバキアでは、農業生産の中で最も大きな比重を占めている生産組織は依然として農業生産協同組合であるし、ハンガリー、ブルガリア、東ドイツ、ルーマニアといった国々でも農業生産協同組合は重要な位置を占め続けている。ここでは触れないが、ロシアでもコルホーズ、ソフホーズの継承法人の大半は、実質的には農業生産協同組合として活動している。 社会主義時代の東欧の集団農場も形式的には農業生産協同組合の形をとっていたが、体制が変わった後の改革により、それらの農場は新しい原則に基づく農業生産協同組合へと組織転換を遂げた。社会主義時代の東欧諸国の協同組合農場は、ロシアから輸入されたコルホーズ的集団農場をモデルにするもので、体制転換後には、それが「真の」あるいは「本来の」生産協同組合に転換したのだと指摘する議論が多く現われた。新しい協同組合農場は、社会主義時代の農場と区別する意味で、「転換された」協同組合農場(transformed cooperative farms)としばしば呼ばれる。 集団農場から新しい協同組合農場への転換がどのように行われたのか、それらは経営体としていかなる特徴を持っているのか、今後、市場経済のもとで、それらの農場は生き残り発展していく力を持つものなのか、という3つの点について考察することにしたい。 |